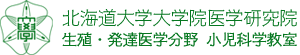自治体ではたらく
中山 加奈子 先生旭川医科大学 2012年(平成24年)卒業

もともと学生時代からずっと小児科に一番興味がありました。初期研修で様々な科を経験するうちに気持ちが変わるかとも思いましたが、研修を終えてみてもやはり小児科が一番楽しく、お世話になっていた市立札幌病院の先生方に付いて行くぞ!という気持ちで北大小児科の門を叩きました。
市立札幌病院時代に糖尿病サマーキャンプに参加したり、初発の糖尿病やバセドウ病を指導医の先生方と診察させていただいたりしたことが非常に深く印象に残っており、内分泌をもっと勉強したいと考え、医師6年目で大学院に入り、中村明枝先生に師事しました。内分泌の専門的な知識を深めていく一方で、院の研究テーマが甲状腺機能と肥満に関連するものだったので、肥満ひいては生活習慣病の予防についても考えているうちに、公衆衛生の面白さや重要性を感じるようになりました。臨床はやりがいがありましたし、内分泌の勉強も楽しかったのですが、院の卒業が良い区切りだと思い、思い切って札幌市の仕事に飛び込みました。

現在は主に地域の母子保健に関連する仕事を行っています。小児科と共通することとしては乳児健診が挙げられます。看護師、保健師、歯科医師、心理士等、多職種で地域の子ども達や発育・発達やそのご家族の不安、悩みの解消に努めています。これまでは疾患のあるお子さんを迎え入れる立場でしたが、今は疾患だけではなく、家族全体の生活も含めてどのように支援し、サポートしていくかという広い視点が求められているように感じます。乳幼児健診のマニュアル改訂に携わったり、3歳児健診への視覚スクリーニング導入への準備に取り組んだりという、「枠組みを作る」仕事も自治体の医師ならではの特徴です。
また、市内各区には医師職は1-2名しか居ないので、自分の職場の職員の健康管理も大切な仕事です。産業医の資格も取得する機会をいただけたので、職場環境を整えて職員の心身の健康を守るためには何をしたら良いのか、新たな課題にやりがいを持って取り組んでいるところです。
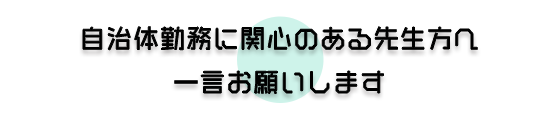
臨床はとてもやりがいがあります。それは間違いありません。でも、自治体の業務は臨床とはまた別の魅力があると思いますし、臨床で積み重ねた経験を発揮する場面も多々あります。子どもに限らず、もっと多くの人の健康を包括的にサポートしたいとの考えを胸に秘めておられるのであれば、私のような仕事も選択肢の一つになるのではないでしょうか。チームで多様な問題に取り組んでいくのが好きな方、お勧めです。
古澤 弥 先生北海道大学 2011年(平成23年)卒業

元々、子どもが好きだったので、学生時代から小児科が第一志望でした。初期研修を横浜の病院で受けたため、そのまま関東圏で後期研修を行うことも検討しましたが、医療機関や医師数が多いため、経験できる症例に偏りがあったり、担当症例数が少なかったりする場合もある、ということを聞き、北海道の地方病院で充実した研修ができる北大小児科へ入局をさせていただくことになりました。
そのまま臨床を続ける予定でしたが、後期研修2年目のときに、娘が重症新生児仮死で出生して重症心身障害児となり、臨床を続けることが難しくなってしまいました。そこで、縁あって平成28年より札幌市に行政医として入職することになりました。
 COVID-19第4波の報告会
(左端が筆者、市長、副市長、DMATの先生方と)
偉い方に肖像権があったらまずいのでニコちゃんマークで失礼します。
COVID-19第4波の報告会
(左端が筆者、市長、副市長、DMATの先生方と)
偉い方に肖像権があったらまずいのでニコちゃんマークで失礼します。

札幌市の行政医の勤務先は、大まかに以下の2つに分かれます。一つが、保健所(感染症対策、医療政策など)で、もう一つが、各区保健センター(乳幼児健診、虐待防止など)です。その他、希望があれば、札幌市子ども発達支援総合センター(通称ちくたく)の児童精神科で働くことも可能です(同門の先輩がいらっしゃいます)。また、出向という形で、北海道庁、厚労省、国立感染症研究所などでの勤務の道もあるようです。
私は、最初の2年間を白石保健センター、次の3年間を保健所感染症総合対策課、そして、今年4月から中央保健センターで勤務をしています。また、保健所勤務の最初の2年間は、週1日「ちくたく」の児童精神科で勉強をさせていただきました。
行政に入って、議会対応、報道対応、事故調査など、様々な経験をさせてもらっていますが、特に印象に残っている経験を二つ紹介させていただきます。
一つ目は、災害派遣です。平成30年7月豪雨の際に、災害時健康危機管理支援チーム(DHEAT : Disaster Health Emergency Assistance Team)として、被害の大きかった広島県呉市の支援に入りました。DHEATは、医師、保健師、事務職等で構成され、被災した自治体を支援するチームです(DMATの真似をして厚労省が作ったものです)。行政経験に乏しい私が、なぜか先発隊のリーダーとして派遣されました。全国的にも派遣が珍しかったため、現地で追っかけ取材があり、小さくですが全国紙デビューしました。現地の方々にどれだけお役に立てたかは分かりませんが、被災地の悲惨な状況を目の当たりにし、非常に貴重な経験をさせていただきました。
二つ目は、COVID-19の対応です。令和元年12月に中国武漢で新型肺炎が確認された当時、運悪く”感染症”総合対策課で勤務していたため、札幌市1例目から現在までずっと関わっています。当初は、検査受付~検体採取~入院調整~患者搬送まで全て行っていましたが、その後は業務が細分化され、現在は、主にクラスター対策の業務を担っています(中央保健センターとの兼務)。初期の頃にお世話になった国立感染症研究所やDMATの先生方からの指導をもとに、保健所看護師と一緒に医療機関や施設を訪問して、情報整理や感染対策の助言などの支援を行っています(こちらは上司が非公式にSCCAT : Sapporo COVID-19 Cluster Assistance Teamと命名して活動しています)。第3波では200人規模の精神科病院クラスター、第4波では80人規模の高齢者施設クラスターの対応も行いました。第4波では市内が医療崩壊を起こしていたため、高齢者施設での医療提供、お看取りの対応など、感染対策以外の社会的な問題が多く存在する中での支援はとても困難な状況でした。
 札幌市DHEAT出発式
(左列中央が筆者)
札幌市DHEAT出発式
(左列中央が筆者)
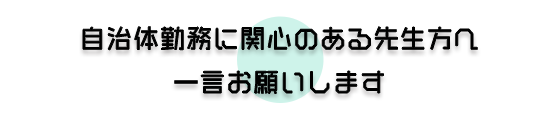
札幌市は、各区保健センターで乳幼児健診などの母子保健分野を担当しているため、15名程度の行政医のうち7-8割が小児科医です。北大小児科の同門の先生方も多くいらっしゃっています。正直なところ、バリバリの臨床や研究をしている先生方からは、物足りなさを感じると思います。しかし、事件が起きると大きいのと、なかなかできないような経験ができるため、確実に世の中の見方は変わると思います。