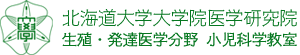育児との両立(男性医師編)
大畑 央樹 先生弘前大学 2011年(平成23年)3月卒業

- 出身が北海道であったため、北海道で小児科医として仕事をしたかった。
- 後期研修を独自で就職活動を行い、他院で採用してもらえていたが、3年目に人事調整が難航していたところ、北大小児科に移行の研修体制を整えてもらえたため。

仕事で家を離れているときはどうしても妻に任せっきりになってしまいます。そのためGo Home Quicklyの精神で、できるだけ時間外労働にならないよう日中のうちにできることは進めてしまい、早く帰宅するように意識しています。
帰宅後や休日は一定時間めいっぱい構います。構いすぎると私がいないときに同じことを妻にしてもらおうとするため妻へ負担がくることと、長すぎると私も疲れて休めないので、ある程度時間を決めています。昨今のご時世でなかなか大変ですが、子供を外に連れ出して、目の届く範囲でしっかり体を動かしてもらい大人は休むという裏技も使ってます。欠点は我が強すぎてなかなか終了といっても聞いてくれず駄々をこねられず妻の雷が落ちることです。
今年度からは幼稚園にも入園したので習い事もさせつつ、習ったこと・やってきたことを尋ね、答えられないときは思い出せるよう促すこともしています。悲しいことに(宿命かもですが)自閉傾向がまずまず強いので自分の話したいことだけしゃべって、質問への返答がかえってこず、これだけで数時間かけることもあるのですが・・・
上でだらだら書いてしまいましたが、基本的には妻の負担を減らしつつ、しっかり子供とスキンシップをとるということを重点に置いています。
ただもちろんこれは私だけではなしえないことです。休日の学会や研究会があれば、子供が割り込んでこないよう妻がサポートしてくれます。そして長期出張などで家を空ける際には母方祖父母・父方祖父母の力も借りています。その際はお礼をしつつ、互助の精神で今のところなんとかやってこられているのかなと考えています。
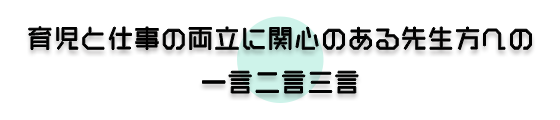
小児科を志す人に子供が嫌いという人はいないと思っています(偏見?)。なので基本的に育児というものは子供と接していろいろなことをするので、楽しいと思ってもらえると思います。もちろん楽しいだけではなくいろいろ苦労もあります。本で読んだことや患者さんから相談されていたことだけではない、さまざまな不安や問題にさらされることもあります。正直それが気になって仕事が手につかなくなることもありました。ただその苦労もその時だけで後になってはいい思い出になるかもしれないですし、なによりその経験は実臨床でかなり役立ちます。患者さんの親御さんとお話をするときに実体験をもとに話すようになったので、より説得力が出たと私自身は感じています。
正直仕事で疲れたから構うのしんどいってこともなくはないですが、その辺りは奥様や周りの方々と相談をお願いします。なにより育児の一番の功労者である、奥様を大切にしてあげてください。

佐々木 大輔 先生岩手医科大学 2008年(平成20年)卒業

もともと北海道出身で大学卒業とともに戻ってきました。北大小児科へは研修医のローテーションで研修した際に、やりがいを感じ、北大小児科に進むことにしました。

妻(医師)と共働きで子育てしています。私自身の仕事内容から、育児については妻の負担がかなり大きいと感じています。また、双方共に祖父母などの親族が近隣に住んでおらず、簡単に子供を預かってもらうことなどが難しいため苦慮しています。少しでも家事負担などを減らすために、家事代行サービスの利用、家電の充実化を図るなどの工夫をしています。子供の送迎には、移動支援ヘルパーやタクシーによる移動支援の利用を行っています。その他としては、子供が病み上がりの時期には病児保育の利用、通園している保育所・幼稚園での預かりが難しい場合には他の保育所で行っている一時預かりの利用もしています。また放課後デイ・アフタースクール・ミニ児童会館の利用、シッターの利用など、考えられる社会資源を、目いっぱい活用しています。
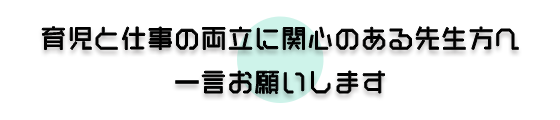
共働きで子育てをする以上は、仕事も完璧、家事も完璧、育児も完璧という理想を実現することは不可能です。仕事、家事、育児を共働きで行うには、周囲の協力と理解および、社会資源の活用が必須であると思います。ある一定のところまでとして完璧を追わず、そして考えすぎて精神的・体力的に追い詰められないように妥協をすることが必要だと思います。大変ですが、楽しくやっています。
早坂 格 先生旭川医科大学 2006年(平成18年)卒業

幼少期から北海道で育ったため、小さい頃から北海道で働こうと思っていました。北大小児科は各分野をまんべんなく学ぶことができ、また、全道各地に関連病院があるため、研修医の頃に幅広い知識を身につけながら全道各地で仕事ができると思ったからです。

育児と仕事を両立していると言うと、(妻から)苦情がくるので、育児と仕事を両立するために努力していることを書きます。正直なところ、育児も仕事も両立していると言えるほどできていません。
最初に、育児についてです。私には子供が3人(小5、小3、5歳)います。学校・保育園や習い事の送り迎えは妻や義父にほとんどしてもらっており、掃除や洗濯や普段の料理も妻にしてもらっています。つまり、育児は「ほとんど」妻がしています。唯一私がしていることは、休日の料理です。いかに簡単でおいしいものを作れるか、時間がある時にyou tubeを見て勉強しています。炒飯および卵や竹輪を使った簡単な料理は子供からも人気があります。子供と一緒にごはんを作ることもありますし、家の前でバーベキューをすることもあります。それぞれの都合が合う時には、夏はキャンプ、冬はスキーをして過ごしています。家にいると、テレビを見たりゲームをすることが多くなってしまうので、できるだけ外へ出て一緒に遊ぶようにしています。
次に、仕事についてです。私を含めて一緒に働く先生が皆、仕事と休みのメリハリをつけられるように配慮しています。仕事の性質上、時間外勤務は少なくないのですが、可能な限り勤務時間内にしっかり仕事をし、夜間や休日は当番の先生に仕事を託すようにしています。夜間や休日の当番では大変な時もありますが、プライベートの時間をお互い気持ち良く持てるように努力しています。
また、育児や仕事を継続するためには、健康や体力の維持が必要だと健康診断の度に思うようになりました。片道9kmほどの車通勤を、2-3年前から春〜秋の天気が良い日には自転車通勤に変更し、月に2-3回ほど、職場の方々とバドミントンをして体力や健康を維持するように努力しています。
良いことばかり書きましたが、決して良いことばかりではありません。作ったご飯が不評だったり、子供たちは言うことを聞かないこともあり、また娘は反抗期にはいりつつあります。仕事もいつもうまくいくとは限りません。運動や自分の趣味の時間をつくることにより、適宜、自分自身もリフレッシュすることが育児でも仕事においても必要であると思います。
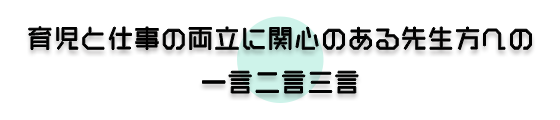
育児があまり得意ではない私が思うことは、
- 育児について謙虚になる事(一番大変なのは私ではなく、言うまでもなく妻なので、妻への感謝を忘れてはいけません)。
- 家庭では可能な時間に自分ができることを一つで良いので続ける事(得意なことを一つ作り、誠意をもって継続しましょう。下手であっても、いずれ家族に伝わるはずです)。
- 自分の趣味の時間をつくり、リフレッシュする事(忙しい中でも、時間を作りましょう)。
- 育児も仕事も無理をしてはいけません。困難である場合には、周囲の人に相談しましょう。